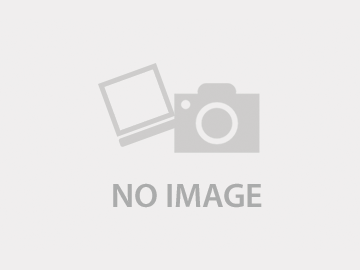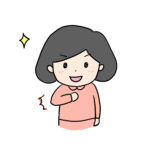「不登校だった時に親や友達、学校にしてほしかったことはありますか。」
という質問に元不登校が答えます。あくまで私の考えですので参考程度にどうぞ!
不登校の時に求めていたもの①不登校扱いしないで
不登校扱いするなって、不登校だろ!?って感じですが(笑)、圧倒的に私が求めていたものはこれです。
不登校になる前は、「私は○○が好き、○○が得意」など、自分のアイデンティティがたくさんあったはずなのに、学校へ行かないという選択をした途端、「不登校」というラベルを張り付けられた気がしました。
中学生の頃、休日に複数人の友達と遊ぶ予定を立てていた時に、そのうちの一人から「学校に来ない人とは遊びたくない」と言われたことがありました。私は不登校である前に一人の人間なはずなのに、「学校へ通っている子/不登校」という2項対立の中に自分のアイデンティティが落とし込まれている気持ちになりました。
とはいえ、10年前はまだ不登校に対するイメージがネガティブなものが多かったので仕方ないことですし、自分自身で不登校をアイデンティティにしていた側面があったことも確かです。
不登校の時に求めていたもの②原因を探らないで!
自分の子どもや友達が不登校になったら、「どうして?」と思うことは、不登校を経験したことがない人からしたら自然なことだと思います。
ですが、私が自分が不登校になった理由を明確に言語化できたのは20歳を超えてからでした。不登校になってから6年以上経っていました。
中学生の頃の私には、学校教育を含めた日本の社会の仕組み、その中で不適合を起こしている自分という存在を客観視して、不登校になった原因を分析する方法を持ち合わせていませんでしたし、自分の状況を説明できる語彙も知りませんでした。
そのような状況で、学校の先生や友達に「なぜ学校に行かないのか」と事あるごとに問われることは苦痛でした。
口には出さなくても「どうして行かないんだろう」と思われていると思うと肩身が狭かったです。
仮に原因が分かっていたとしても、不登校が維持されている要因は別のところにある可能性もあります。場合によっては、その維持要因に目を向けるほうが解決への道だったりするのです。
不登校の時に求めていたもの③不登校に関する情報
当時はインターネットを使っても、不登校経験者のその後に関するポジティブな情報を得ることがなかなかできませんでした。
高校受験が近づいていた時期には『不登校 高校受験』というワードで一日中検索をかけて情報収集していたこともあります。今ほど不登校の存在が世間に認知されていなかったので、学校の先生も不登校の生徒には私立の受験を薦めるしかなく、手探りだったようです。
今は、このような個人ブログやSNS、YouTubeなどで不登校に関する情報を簡単に得ることができますが、逆に情報過多なところもあるので、不登校の子どもたちの情報収集をぜひサポートしていただければと思います。
終わりに
今回は、「不登校の時に周りに求めていたもの」について書いてみました。不登校当事者や経験者のみなさんには共感してもらえる部分があるのではないかな~と思いますが、最初にも言った通り、あくまで私個人の考えですので、その点はご了承願います。