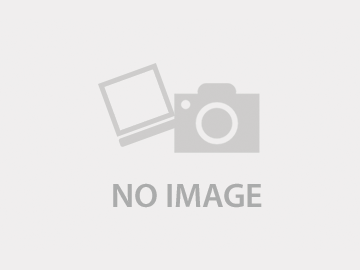不登校のきっかけのあるあるネタの1つだと思っている。
「給食の完食指導」
小さい頃から食べるスピードの遅い私にはとても辛かった…。
学校給食はその栄養管理が学校給食摂取基準に基づいて行われていて、家庭での食事で摂取量が不足している栄養素を可能な範囲で補う工夫がされるなど、子どもの健康を考えた超ありがたいシステム。
だから、このような恵まれた環境に対して「辛い」なんて言うのは贅沢だし、給食を作ってくれていた人に申し訳ない気持ちがあるのだけど、でも、私は給食の完食指導に苦しんだ過去がある。
そして20歳を過ぎるまで「食事」にトラウマを抱えることになる。
始まりは小学5年生。当時の担任によって突如始まった「完食しないとダメ」という完食強要。身に覚えのある人も多いのではないでしょうか。
それまでの私は野菜が少し苦手なくらいで、特別な好き嫌いがあるわけでなく、基本的に何でも食べられた。ただ、小さい頃から食べるスピードが周りより遅かった。だからみんなと同じ量を盛られると、もちろん時間がかかる。しかも給食の時間は約15分。はい、無理です。
そして通告された
「食べ終わるまで遊びにいけません。」
削られた私のお昼休み。
食器や食缶はみんなのペースで先にコンテナに戻されるから、お昼休みにとぼとぼと一人で給食室まで返しに行く。
苦しんでいたのは私だけではなかった。
吐き気を催すほど苦手な食べ物を泣きながら食べている子もいた。
まだ食べてるの?と担任から急かされる日々、
お昼休みに友達と遊べない悲しみ、
気づけば、おいしくて楽しい時間のはずだった給食が地獄になってしまっていた。
そして、ある日突然体に異変が起きた。
食べ物が飲み込めない。
嚥下が正常に行われなくなったのだ。
何回嚙んでもごっくんができない。超困った。焦った。
どうして飲み込めなんだろう。どうして私は食べるのが遅いんだろう。みんなはできるのに。
しかし小5の私は早いうちに悟った、多分この状況を理解してくれる人間はここにはいない。
担任にばれないようにどうしても飲み込めないものをトイレまで吐きに行くしかなかった。
(ごめんなさい)
給食の献立を見て、嚥下に支障をきたす可能性の高いもの(水分の少ないもの)が出る日に学校を休んだこともある。
学年が変わって6年生になっても担任は同じ先生だったから、私は小5からの2年間毎日ストレスと闘いながら生きることとなった。
この話の中で一番恐ろしいことは何だろうか。
それは、「完食しろー」と圧をかけてくる担任ではなく、
食べられる量や食べるスピードが人によって違う、という当たり前のことにすら気づけない小学5年生が、食べるのが遅い、嚥下ができなくなったのは自分が悪いのだと思い込んで、誰にもSOSを出せなかったということ。
人に弱みを見せられない私の性格にも問題はあったと思うけど、家族にも、友達にも、もちろん先生にも言えなかった。
この給食のトラウマは根深く、私は大学生になって友達が食べることの楽しさを教えてくれるまで、親友や家族以外の人との食事を避けていた。
今では友達のおかげもあって食べることが楽しいし、食事の大切さも知った。
一方で残念ながら教育実習など、学校という場での食事に今でも困難を抱えている。
学校そのものに苦手意識があることも影響を与えていると考えられるが、学校内での食事は嚥下が困難になってしまう。
今回この記事を書いたのは、今では減っていると信じているが、理不尽な完食指導に苦しむ子どもの存在が少しでも認知されて欲しいと言う気持ちと、大人から子どもの世界がどれだけ見えていないか、自分自身にも忠告する気持ちからです。
最後に、完食指導について私の考えを述べておく。
私は”完食指導”自体は教育上大切なことだと認識している。
下記の学校給食の目標に照らしても、完食指導を含め給食の時間を通して子どもたちに食育を行うことは教師の役割である。
(1)適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。
(2)日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。
(3)学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。
(4)食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
(5)食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。
(6)我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。
(7)食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。
だから完食指導は悪くない。
その子の食べられる量の範囲内で行われていれば。
少し前から完食指導が会食恐怖症や、私のような嚥下障害発症のきっかけになることが認知されるようになってきていて、最近では食事に手を付ける前に、自分の食べられる量に調整させる先生が増えているようです。
どうか子どもたちが食べる喜びを失わない楽しい給食の時間でありますように!
食に関する指導の手引-第二次改訂版-(平成31年3月):文部科学省
 双極症
双極症