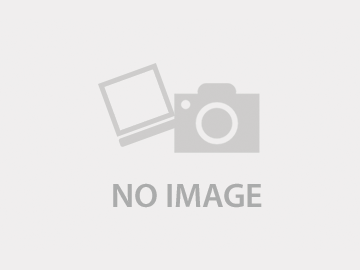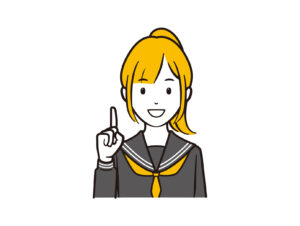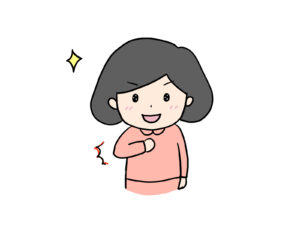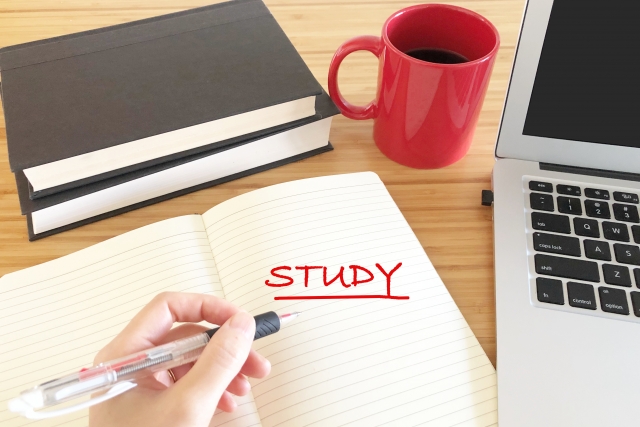
不登校や学年ビリのような状況から名門大学合格のような下剋上を果たすと
1度は言われる、あるいは言ってしまいそうになる言葉。
「地頭が良かったんだね」
ビリギャルのモデルである小林さやかさんも当時から、そして今でもなお言われることがあるらしい。
もちろん(?) 私も言われたことがある。
私は18歳当時中学2年生レベルの学力から、1年間猛烈に勉強し国立大学合格を果たした。
私が合格したのは、小林さんが入学した慶應義塾大学のような名門大学ではなく、
地方の国立大学だったけど、それでも一部の人から
「え、前例ちゃんって実は頭良かったんだね」とか
「地頭が良かったから合格できたんだよ」と言われた記憶がある。
確かに、1年間の努力を地頭が良いの一言で片づけられると、
頑張ったことへの評価が一気に下げられた感覚にならんでもない。
おまえはもともとできるやつだったのだと。
とは言え、当時、私が勉強する姿を間近で見てくれていた家族や友人は
「頑張ったね~!努力したね」と頑張りを評価してくれていたから、
他人に”地頭が良いから”と言われたことはあまり気にしていなかった。
それに、私の場合は地頭が良かったと言われればそうなのかもしれない。
いや、1年間相当勉強して誰にも負けないくらいの努力をしたことは確かなのだけれど、
私と同じ量の勉強をすれば誰もが1年で合格できるのか
と言われると多分それは違うから。
私が比較的短期間で結果を出せたのは、支えてくれた家族や友人、先生の存在はもちろん、
自分に合った学習方法や、効率よく多くの情報を吸収する方法を知っていたからというのが大きいと思っている。
小林さんのブログを引用させていただくと、
『学び方や感じ方はそれぞれ違うし、得意不得意ももちろんある。知識詰め込み型の勉強が得意な子もいれば、対話を通して言語化するのが得意で、そこから学びを吸収する子もいる。褒められたらもっと頑張れる子もいれば、叱られてこんちくしょうで頑張るほうが結果が出やすい子だっている。』
これに尽きるのだが、人それぞれ「学ぶ」という行為への向き合い方は違っていて、
最も成果の出る勉強方法も個人で異なる。
そしてこのことを自分自身もしくは、指導者が認識できているかどうかで結果も大きく変わってくるということなのだと思う。
私は、勉強=自分の知りたいことを知ること=楽しいもの
という感覚で生きていたから、当時多くの高校生がやっていた単語帳とのにらめっこや、ひたすら問題集を解きまくるというような晩強方法は一切行わなかった。
自分には合わないことを知っていたし、自分にとってそうすることでの学習効果がいかに低いものであるかを認識していたからだ。
そして、この自分に適した学習方法をよく理解していることを地頭の良さを構成する1要素と考えるのならば
私は確かに地頭が良かったと言える。だからそう捉えると「地頭が良い」はけっこう褒め言葉だったりする。
ただ、ここで問題にされるのは
地頭の良さが生まれ持った才能なのか否かという点なのだろう。
この話を深堀することにどこまで価値があるか定かでないが
私が調べた限り、「地頭」という言葉をテーマに扱った論文はヒットしないし
地頭という言葉自体、かなり曖昧な言葉で、個人の感覚で使われているようだ。
例えば、地頭の良さを、「記憶力の良さ」や「論理的思考力」のような具体的な能力に細分化するのならば、ある程度、遺伝子レベルの話に帰することができそうだが、仮にそうしたところでどうするのだろう。
ポジティブな方向に議論が進めば良いが、
地頭が悪いから
というかなり不安定な理由で自分にはできないと、行動を起こす前から夢を諦めたり、
はたまた他人に向けて使うことで、傷つけたり、夢を諦めたりすることがあってはならない。
これは私が地頭の良い(かもしれない)人間だから言えるのだと言われたらそれまでなのだが、
私は人とズレていたり、苦手なことがいっぱいある。
お店の名前や人の名前は、漢字で書かれている場合だいたい間違える。東横インをずっと「とうおういん」と呼んでいたし、人の顔を覚えることが苦手で、最近まで高橋優さんと成田悠輔さんが同一人物だと思っていた、、、。(ごめんなさい)
みんな得手不得手がある、といかにも浅そうな結論に辿り付いてしまったが、結局そうで。
今ある自分に与えられた装備でどこまでやるか、さらにその装備をさらにどう磨いていくのか、
そっちに力を入れた方が楽しいし、可能性は広がると思うのです。