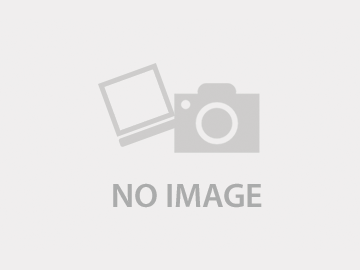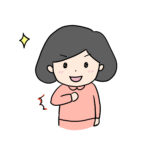双極性障害の「躁状態」は、気分が高揚し、エネルギーが爆発的にあふれる時期です。頭の回転が速くなり、アイデアが次々と浮かび、まるで「何でもできる」ような感覚になることもあります。しかし同時に、感情の起伏が激しくなり、怒りや焦り、苛立ちが一気に噴き出すことがあります。その結果、思わず暴言を吐いてしまったり、周囲を傷つけるような行動を取ってしまうケースが少なくありません。
躁状態では、脳の興奮が高まり、物事を冷静に判断する力が低下します。たとえば、誰かに注意されたときに「自分を否定された」と過剰に感じ、強く言い返してしまう。相手の言葉を最後まで聞けず、感情のままに反応してしまう。こうした反射的な言動は、本人にとっても予想外のものであり、落ち着いた後に「どうしてあんなことを言ってしまったんだろう」と深く落ち込むことが多いのです。
暴言の背景には、「万能感」と「焦燥感」が入り混じった心理状態があります。躁のピーク時には、何事にも自信を持ち、周囲の意見を聞く余裕がなくなります。「自分のほうが正しい」「理解してもらえない」と感じることで孤立感が強まり、それが怒りとして噴き出してしまうのです。一方で、心の奥には不安や恐れも潜んでおり、それを打ち消すかのように強い言葉で相手を攻撃してしまうこともあります。
また、睡眠不足やストレスも暴言を助長します。躁状態では眠れなくても平気だと感じますが、実際には脳が休まっていません。疲労が重なることで感情のブレーキが効かなくなり、小さな出来事でも爆発的に怒ってしまう。これは、双極性障害の典型的な症状の一つです。周囲から見ると「怒りっぽくなった」「性格が変わった」と映るかもしれませんが、本人の意識ではコントロールできない状態にあるのです。
躁状態の暴言は、人間関係に深い溝を作ることがあります。特に家族やパートナーに対して暴言を吐いてしまうと、相手が強いショックを受け、距離を置かれてしまうこともあります。後で謝罪しても「また同じことを言うのではないか」と警戒され、信頼を取り戻すには時間がかかります。その一方で、本人も「自分は人を傷つける存在なのではないか」と罪悪感を抱え、うつ状態に転じることも少なくありません。
こうした悪循環を断ち切るためには、まず「躁状態のサイン」を自分自身が把握することが大切です。たとえば、「睡眠時間が減っている」「口数が増えた」「周囲にイライラする」などの変化に気づけると、早めに主治医に相談できます。気分記録アプリや日記などを活用して、客観的に状態を振り返るのも有効です。また、周囲の人が「今少しテンションが高いかも」と気づいたときに、優しく声をかける環境があると再発防止につながります。
そして何より大切なのは、「暴言を責めすぎない」ことです。躁状態の行動には、本人の意思ではどうにもならない部分があります。もちろん、傷ついた相手への配慮は必要ですが、同時に「病気の一部だった」と受け止め、回復に向けて前向きに歩むことが、再発を防ぐ第一歩です。自分を責め続けることは、新たなストレスとなり、次のうつ状態を招くリスクにもなります。
双極性障害とともに生きるということは、気分の波とどう付き合うかを学び続けることです。躁状態の暴言も、その中で繰り返し向き合うテーマの一つです。大切なのは、「また起こさないように」と恐れるよりも、「どうすれば早く気づけるか」「どんな支えが必要か」を一緒に考えていく姿勢です。体験談を読むことは、そのヒントを得る大きな助けになります。
以下では、躁状態の暴言や衝動的な行動を経験した方々の体験談を紹介します。リアルなエピソードを通して、同じ悩みを抱える人の気づきや支えになることを願っています。
👉 躁状態の失敗談5選
躁状態での金銭トラブルや暴言など、衝動的な行動による「失敗」をまとめた体験談です。後悔と再出発のリアルが描かれています。
記事を読む
👉 私の隣の双極性障害〜リアルな夫婦の記録〜
躁状態の夫による暴言や暴力、それに直面する妻の葛藤を綴った記録です。家族として支える難しさと希望が描かれています。
記事を読む
※当サイトの記事は、双極性障害などの体験談・経験に基づいて執筆されたものです。
記事内容は医学的な診断や治療を目的とするものではなく、自己判断の材料として用いることはお控えください。
症状に関しては必ず医療機関・専門医にご相談ください。
参考文献・参考サイト
- 厚生労働省 こころの病気「双極性障害」について:https://www.mhlw.go.jp/
- 日本うつ病学会 双極性障害診療ガイドライン:https://www.secretariat.ne.jp/jsmd/