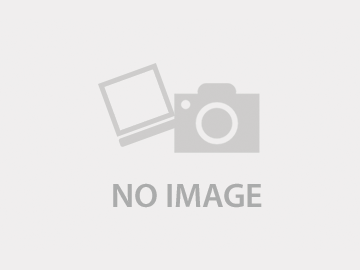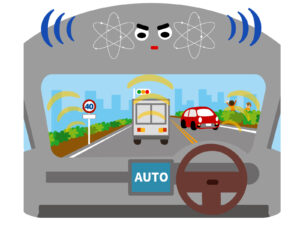双極性障害では、気分の波とともに生活リズムや食欲にも大きな変化が現れることがあります。特に、躁状態(または軽躁状態)とうつ状態では、同じ「食欲の変化」といってもその方向性がまったく異なることがあります。今回は、研究で知られている一般的な傾向と、実際に体験を記録されている方々の記事を紹介しながら、「双極性障害と食欲」の関係を考えてみたいと思います。
もくじ
躁状態では「食べすぎる」人も「食べ忘れる」人もいる
躁状態では、活動量が増えたり、衝動性が高まったりするため、「つい食べすぎてしまう」「甘いものや炭水化物を無意識にたくさん摂ってしまう」というケースがあります。海外の医療サイトでも、躁状態の人が過食や衝動的な飲食行動を取ることがあると指摘されています。
一方で、まったく逆のパターンもあります。躁状態ではエネルギー感が強く、頭の回転が速くなるため、「食べることを忘れてしまう」「空腹を感じない」といった人も少なくありません。実際、医学論文では躁期の被験者の一部で、食欲促進ホルモン(グレリン)の値が低下していたという報告もあります。
つまり、躁状態における食欲の変化には「過食傾向」と「食欲減退傾向」の両方が見られ、人によってまったく違う方向に出るのが特徴です。
うつ状態では「食欲が落ちる」傾向が多いが、例外もある
うつ状態では、気分の落ち込みや意欲の低下に伴って、食欲が減少することが多く報告されています。朝食を抜いたり、食べる気力が湧かず体重が減ってしまうという人もいます。一般的な精神科ガイドラインでも、「うつ期には食欲低下や体重減少が見られることが多い」とされています。
ただし、これにも例外があります。特に「非定型うつ」と呼ばれるタイプのうつ状態では、逆に食欲が増して過食に走るケースがあることが知られています。「気分が沈んでいるのに、食べることで一時的に安心感を得る」というように、心理的なバランスを取るために食事量が増える人もいます。
混合状態ではさらに複雑に
双極性障害には、躁とうつの症状が同時に出る「混合状態」と呼ばれる時期もあります。この時期は気分が不安定で、衝動的に食べてしまう一方で、後から強い自己嫌悪に陥るなど、摂食行動がさらに複雑になる傾向があります。実際、摂食障害を併発する双極性障害の方も少なくありません。アメリカの研究(McElroyら, 2010)によると、双極性障害を持つ人のうち約14%が何らかの摂食障害を併発していることが報告されています。特に過食性障害や過食・嘔吐型(過食症)の傾向が多く、気分の波と食行動の乱れが密接に関連しているケースも見られます。
このように、食欲の変化は単なる気分の一部ではなく、時に「摂食のコントロール」にも影響を及ぼすことがあります。したがって、双極性障害の治療やセルフケアの中で「食事との付き合い方」を意識することは、とても大切なポイントといえるでしょう。
食欲の変化を「自分のサイン」として観察する
食欲の変化は、気分の変動をいち早く知る手がかりにもなります。「最近食べすぎている」「まったく食欲がない」という変化に気づいたとき、それが単なる生活習慣の問題なのか、それとも気分の波の一部なのかを意識してみることが大切です。
また、食事内容が乱れやすい時期には、無理にコントロールしようとせず、医師や家族に相談したり、栄養バランスを意識した軽食を取り入れるなど、小さな工夫を続けていくことが現実的です。
関連する体験談の紹介
実際に双極性障害と食欲の関係について記録されている方のブログ記事を2本ご紹介します。
👉 私の双極生活 食事・躁状態編③
躁状態のときの食欲や食事のコントロールについて、具体的な体験をもとに記録されています。
記事を読む
👉 食欲と躁と鬱
躁のとき・うつのとき、それぞれで食欲がどう変化するのかを、実際の心の動きとともに綴られています。
記事を読む
※当サイトの記事は、双極性障害などの体験談・経験に基づいて執筆されたものです。
記事内容は医学的な診断や治療を目的とするものではなく、自己判断の材料として用いることはお控えください。
症状に関しては必ず医療機関・専門医にご相談ください。