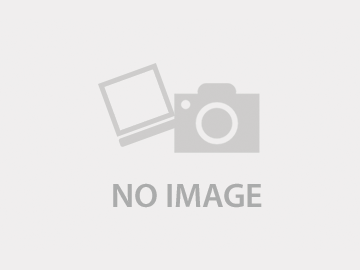双極性障害を抱えながら海外で暮らそうというのは、大きな決断です。言葉や文化、医療体制の違いがある中で、健康状態を保ち続けるには、周囲のサポートと自分自身での調整の両方が必要になります。今回は、実際に双極性障害を抱えながら海外へ移住した方々の体験を参考にしながら、海外移住のリスクや工夫について考えてみたいと思います。
まず最初に直面するのは「医療の問題」です。日本のように精神科や心療内科が身近にある国ばかりではありません。国によっては精神疾患に対する理解がまだ浅く、受診のハードルが高い地域もあります。また、保険制度が異なるため、薬の価格が高額になることもあります。たとえばアメリカでは、保険に加入していないと一回の診察や処方だけで数百ドルを超えることも珍しくありません。
このため、移住前に「どのような医療制度があるのか」「現地で精神科を受診できるか」「日本の医師から紹介状をもらえるか」を確認しておくことが重要です。最近ではオンライン診療や海外からのメール相談に対応している日本の医療機関も増えています。言葉の壁が不安な場合は、日本語対応のカウンセラーを探すのも一つの方法です。
次に考えるべきは「生活リズムと環境の変化」です。双極性障害の症状は、生活リズムの乱れによって悪化しやすいと言われています。特に時差の大きい国へ移動すると、睡眠のリズムが崩れ、躁状態やうつ状態が出やすくなることがあります。移住直後は「観光モード」になって活動的になる一方で、落ち着いた頃に疲れが出て落ち込む人も多いようです。
そのため、海外では「自分で自分のリズムを守る意識」がより一層大切になります。現地の生活に慣れるまで、睡眠・食事・運動の時間を意識的に一定に保つよう心がけるとよいでしょう。また、信頼できる友人やサポートネットワークをつくっておくことも心の安定につながります。SNSやオンラインコミュニティを通じて、同じように双極性障害を抱えて海外で暮らしている人とつながるのも有効です。
もう一つ見落としがちなのが「薬の継続」です。国によっては日本で使っている薬が認可されていなかったり、入手が難しい場合があります。そのため、医師と相談して「現地で手に入る代替薬」を確認しておくことが必要です。また、薬を持ち込む際には、医師の診断書や英文の処方箋を準備しておくと入国時のトラブルを防げます。
一方で、海外移住によって新しい価値観や生き方に出会い、気持ちが楽になったという人もいます。日本では「病気であること」を負担に感じていた人が、海外では個性の一つとして受け入れられたという声もあります。異なる文化に触れることは、自己理解を深めるきっかけにもなるのです。
とはいえ、海外での生活は決して楽ではありません。言葉が通じない不安、孤独、気候の違い、行政手続きなど、心身にストレスを与える要素が多く存在します。双極性障害の症状が安定していない時期に移住を決行すると、再発や体調悪化のリスクもあります。したがって、移住を検討する際は、主治医とよく相談し、症状が比較的落ち着いているタイミングを選ぶことが大切です。
新しい環境の中で自分を試しながら、無理をせず、必要なときには助けを求める。そのバランス感覚こそが、双極性障害を抱えながら生きていくうえで最も大事なのかもしれません。
関連記事紹介
👉 【双極性障害のアメリカ移住】かかりつけ医を見つけるまで
アメリカでの生活を始める中で、医療機関を探し、自分に合った主治医を見つけるまでの過程を丁寧に綴った体験談です。
記事を読む
👉 双極性障害と留学②
留学生活の中で直面する体調管理の難しさや、周囲との関わり方など、リアルな葛藤が描かれています。
記事を読む
※当サイトの記事は、双極性障害などの体験談・経験に基づいて執筆されたものです。
記事内容は医学的な診断や治療を目的とするものではなく、自己判断の材料として用いることはお控えください。
症状に関しては必ず医療機関・専門医にご相談ください。