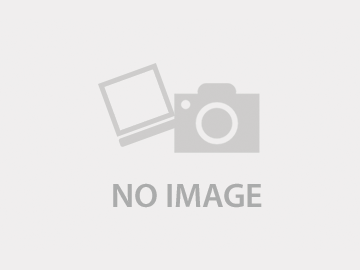双極性障害(躁うつ病)は、気分の波が大きく変動する精神疾患であり、診断の難しさがしばしば指摘されています。うつ病や統合失調症などと症状が似ている部分も多く、誤診が生じることも少なくありません。そんな中で注目を集めているのが「光トポグラフィー検査」です。この記事では、実際に光トポグラフィー検査を受けた方の体験談を紹介しながら、この検査がどのようなものなのかをわかりやすく解説します。
もくじ
光トポグラフィー検査とは?
光トポグラフィー(NIRS:近赤外分光法)検査とは、頭部に近赤外線を当て、脳の血流変化を測定することで脳活動を可視化する検査方法です。主に前頭葉の血流パターンを見ることで、うつ病・双極性障害・統合失調症といった精神疾患の特徴を比較することが可能とされています。
この検査では、言語課題を行いながら脳の血流をモニターします。検査自体は痛みもなく、頭にセンサーを装着して座っているだけで完了します。所要時間はおよそ30〜40分ほどです。
双極性障害における光トポグラフィーの役割
双極性障害では、うつ状態と躁状態のどちらの時期に検査を受けるかによって脳活動パターンが変化すると言われています。そのため、光トポグラフィー検査は「診断を確定する」ものではなく、「診断の補助」として活用されます。光トポグラフィー検査について、Youtubeでも活躍されている益田裕介先生は「光トポグラフィー検査は科学的なものではない、研究段階」だと話していますし、同じように渥美正彦先生も、「光トポグラフィー検査が精神科の診断を覆すものであってはならない」と話しています。
実際、厚生労働省もこの検査を正式な診断基準としては認めていません。しかし、医師が臨床的な判断を行う際の参考情報として用いることで、誤診のリスクを下げる一助になると考えられています。
実際に受けた人の体験談
実際に光トポグラフィー検査を受けた方の声を見てみましょう。
1人目の方は、検査前に「自分の病気が本当にうつ病なのか、それとも双極性障害なのかを知りたかった」と語っています。検査の結果、医師から「双極性障害の可能性が高い」と説明を受け、薬の処方内容が見直されたそうです。検査は静かで落ち着いた雰囲気の中で行われ、頭に装着するセンサーも痛みや不快感はなかったとのこと。
また、別の体験者は「検査を受けたことで、ようやく自分の状態を客観的に理解できた」と述べています。医師の診断に加えて、脳の血流データを見ながら説明を受けることで、「見えない病気」に対する納得感が得られたという声も多く見られます。
検査の注意点と限界
光トポグラフィー検査にはメリットだけでなく、いくつかの注意点もあります。まず、この検査結果だけで診断が決まるわけではありません。精神疾患は症状や生活背景、本人の感情変化など多くの要素が関わるため、最終的な診断は必ず医師の総合判断に基づいて行われます。
また、検査の結果には個人差があり、検査時の体調・睡眠状態・服薬内容なども影響を与えるとされています。そのため、光トポグラフィー検査を「診断の一部として利用する」姿勢が重要です。
双極性障害を抱える人にとっての意義
双極性障害は、自分の気分の変化に気づきにくいことがあり、周囲の理解も得づらい疾患です。光トポグラフィー検査は、客観的なデータを通じて自分の脳の状態を「見える化」することで、病気への理解や受け入れを助ける可能性があります。
「自分が怠けているわけではない」「脳の働きとしてこういう波があるんだ」と納得するきっかけになった、という体験談も印象的です。検査を通じて、医師とのコミュニケーションがより具体的になり、治療方針を立てやすくなったという報告もあります。
体験談紹介
ここでは、実際に光トポグラフィー検査を受けた方々の記事を紹介します。
👉 【体験レポ】うつ病・双極症(躁うつ病)・統合失調症|光トポグラフィー検査を受けてきました
光トポグラフィー検査の流れや、検査中のリアルな感想を写真付きで紹介しています。
記事を読む
👉 光トポグラフィー検査、双極性障害。
検査を受けた結果、双極性障害の理解が深まったという体験談。医師とのやり取りや検査後の気づきが率直に書かれています。
記事を読む
まとめ
光トポグラフィー検査は、精神疾患の「見えない部分」を少しでも明らかにしようとする新しい試みです。双極性障害に悩む方にとって、診断を支える補助的な手段として、また自己理解を深める機会として活用されつつあります。今後の研究が進むことで、より精度の高い検査法として確立していくことが期待されています。
※当サイトの記事は、双極性障害などの体験談・経験に基づいて執筆されたものです。
記事内容は医学的な診断や治療を目的とするものではなく、自己判断の材料として用いることはお控えください。
症状に関しては必ず医療機関・専門医にご相談ください。
参考文献・参考サイト
- 厚生労働省「光トポグラフィー検査に関する情報」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000050924.html
- 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所「光トポグラフィー検査の臨床応用について」