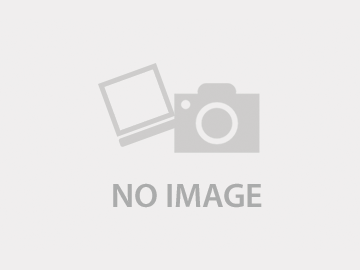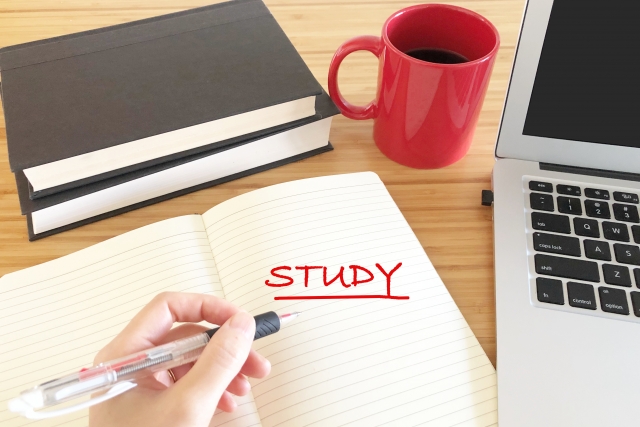
教職経験を重ねた人のブログを読み、「放送大学で特別支援学校教諭免許を取得した」という体験に強く惹かれました。この記事では、まず放送大学で特別支援教員免許がどういう制度で取得できるのかを、体験談を交えてお伝えします。
もくじ
特別支援学校教諭免許状とは何か
特別支援学校教諭免許状は、従来の盲学校・聾学校・養護学校などに分かれていた免許が一本化されたものです。平成19年の学校教育法等の改正で、「特別支援教育の基礎的知識・理解」と「特定の障害についての専門性」を確保するため、大学等で一定の科目を修得することが要件になっています。
放送大学で取得できる人・条件
放送大学では、現職教員などがキャリアアップの一環としてこの免許を目指すケースが多く見られます。制度を利用するには、以下のような条件があります。
- 幼稚園・小学校・中学校・高等学校などの普通教員免許をすでに持っていること。
- 特別支援学校教諭免許を取得する場合には、特別支援教育領域を担任とする教員として、所定の在職年数を満たしていること(通常「3年在職」が条件)。
- 放送大学で、必要となる科目(6~8単位など)を修得すること。どの科目が必要かは、都道府県教育委員会によって扱いが異なるため、申請前に確認すること。
実習は必要か? 通信制の特徴
放送大学はあくまで通信教育大学であり、学生が通う形で教育実習を大学が取り仕切るわけではありません。特別支援教員免許状を取得するためには、通信授業を通して必要科目を履修し、レポート提出や単位認定試験を受けて単位を取得します。大学側が実習を提供する制度ではなく、教職経験や在職年数などが条件として重視されます。
必要な科目・申請手続き
必要科目としては、「特別支援教育基礎」「障害の理解」「知的障害教育」「肢体不自由者教育」など、特別支援教育に関する基礎科目・専門科目があります。どの科目を取るかは、教育委員会との相談のうえでシラバスを確認し決めます。
申請の流れは以下の通りです。
- 居住地の教育委員会に、放送大学で取得した単位で免許申請が可能か確認する。
- 放送大学に出願し、必要科目を履修する。
- 通信授業・単位認定試験をクリアして単位を取得。
- 在職証明書・成績証明書などを揃え、教育職員検定を行う教育委員会に申請する。
体験談から見えるリアル
ここで、実際に放送大学を通して免許を取得した方々のブログを紹介します。リアルな声から制度の実際を感じ取ることができます。
👉 3年間の教職経験を基に、特別支援学校教諭2種免許を取得するハウツー
教職3年の経験をもとに、教育委員会にシラバスを提示し、必要科目を特定。放送大学で履修・単位取得・検定申請までの具体的な手順が丁寧に書かれています。実際の苦労や工夫が伝わるリアルな体験談です。
記事を読む
👉 放送大学に入学した話
通信教育としての勉強スタイルや単位認定試験に向けた準備など、放送大学で学ぶ日常を丁寧に記録しています。通信制で学ぶリアルがわかる貴重な体験談です。
記事を読む
メリットと注意点
メリット
- 仕事を続けながら免許取得を目指せる。
- 必要科目が比較的少なく、負担を抑えて取得できる。
- 教育委員会の認定が得られれば、放送大学の単位で申請可能。
注意点
- 実習を大学が提供しないため、在職年数や経験が重要。
- 教育委員会によって必要科目・単位数が異なる。
- 申請書類の準備や検定手続きに時間がかかる。
- 通信学習のため、自己管理能力が求められる。
まとめ
放送大学で特別支援教員免許を取得した方々の体験談を読むと、制度の仕組みだけでなく、実際にどう動いたのか、どんな苦労や工夫があったのかが見えてきます。通信制という柔軟な制度をうまく活かすことで、現職でも資格取得を目指せる可能性が広がります。