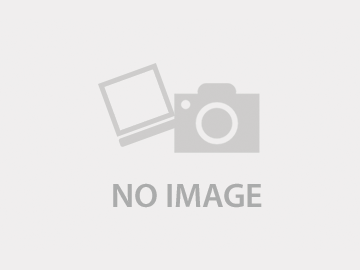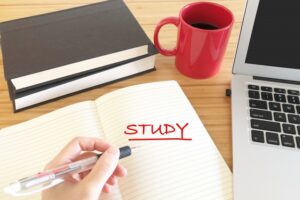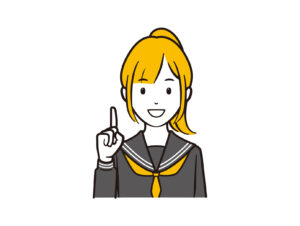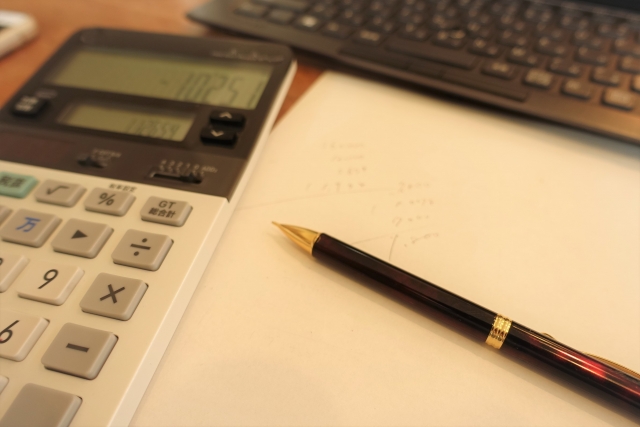
もくじ
1. 教員免許の種類と取得方法
教員免許には大きく分けて「一種免許」と「専修免許」の2種類があります。
一種免許は、一般的に大学の学部卒業時に取得できる免許で、教師としての基礎的な資質を身につけるためのものです。
一方、専修免許は大学院を修了し、より高度な教育活動を行うための専門知識や実践力を求められる免許です。教育者としてのステップアップを目指す上で、この違いは非常に重要なポイントになります。
専修免許を取得する方法は主に2つあります。まず、一種免許を持った上で教育現場での実務経験(一般的に3年以上)が必要です。その後、大学院などで15単位以上を修得することで、専修免許の申請資格を得ることができます。
実際には、各都道府県の教育委員会に申請を行う必要があり、要件は地域によって異なります。そのため、まずは自分の所属する教育委員会の最新情報を確認し、必要な単位や手続きを明確にしておくことが大切です。
また、放送大学のような通信制大学を活用すれば、働きながら柔軟に学習を進めることも可能です。効率的に学び、自身のキャリアアップにつなげましょう。
2. 免許取得に向けた準備
専修免許を目指すには、事前準備が欠かせません。
各都道府県で規定が異なるため、まずは教育委員会の要件を確認することが最初のステップです。特に一種免許から専修免許へのステップアップを目指す場合は、勤務年数や大学院での履修状況が重要になります。
例えば鹿児島県では、「一種免許を所持し3年以上勤務」した上で、「大学院で15単位以上を修得する」ことが条件とされています。こうした条件は県ごとに異なり、年度によって改正されることもあるため、最新情報を確認しましょう。
不明点がある場合は、教育委員会に直接問い合わせることが最も確実です。
放送大学などの教育機関を活用する場合は、履修する科目が免許取得に有効かどうか、事前に教育委員会へ相談することをおすすめします。
特に高校教諭の専修免許を目指す場合、「大学が独自に設定する科目」15単位を修得するケースが多く見られます。自分の専門分野に関連する科目を選び、効率的に学習を進めましょう。
3. 求められる単位と具体的な取得方法
働きながら大学院レベルの単位を修得するのは簡単ではありませんが、正しい手順を理解して計画的に取り組めば、十分に実現可能です。
大学院で単位を取得する方法としては、夜間・週末開講の課程を利用するほか、放送大学のような通信制大学を活用する方法があります。放送大学では「修士選科生」や「修士科目生」として入学でき、必要な単位を柔軟に取得できます。
授業料は1単位あたり約11,000円で、年2回の入学機会があります。試験なしで受講できるため、社会人にも適した仕組みです。
取得した単位をもとに、最終的には教育委員会へ申請を行い、免許状の交付を受けます。
重要なのは、必要な科目を正しく選び、計画的に履修を進めることです。確実に単位を積み重ねていけば、働きながらでも無理なく専修免許を取得できます。
4. 実際の単位取得と注意点
放送大学で専修免許を取得する場合、多くの自治体で「大学独自の科目」15単位の修得が求められます。
さらに「教育の基礎的理解に関する科目」や「教科専門科目」などからも単位を取る必要があります。
高校教諭専修免許を目指す場合には、該当する教科や推奨科目を教育委員会で確認しておきましょう。
放送大学の大きな特徴は、入試がない点です。
「修士選科生」または「修士科目生」として入学でき、共済組合による割引制度を利用できる場合もあります。入学は年2回(4月・10月)あり、働きながらでも学びやすい環境が整っています。大切なのは、自分の生活リズムに合ったペースで継続することです。
また、放送大学の講義はオンライン視聴が可能なため、場所を選ばず効率的に学習できます。
5. まとめ:働きながら専修免許を取得するために
専修免許取得の第一歩は、教育委員会の規定を正確に把握することです。各自治体によって条件や必要単位が異なるため、必ず最新情報を確認しましょう。
次に、大学院や放送大学など、自分に合った学び方を選び、無理のない計画を立てることが成功の鍵です。特に放送大学は柔軟なカリキュラムと費用の手軽さから、多忙な教員にもおすすめです。共済組合の割引制度なども活用し、コストを抑えて進めましょう。
最後に、地道な努力を続ける姿勢が何より大切です。働きながらでも少しずつ学びを重ねることで、確実に専修免許取得へと近づくことができます。自分のペースで、一歩ずつ進めていきましょう。
参考文献・参考サイト
 その他
その他