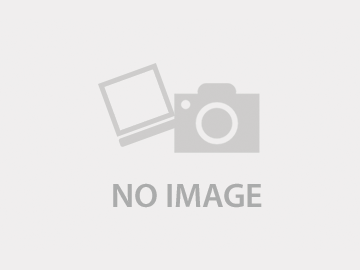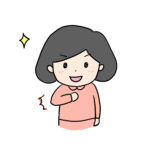双極性障害と付き合っていると、「うつの時間が圧倒的に長い」と感じる人は多いと思います。私もその一人です。気持ちは沈み、体は重く、何をするにも億劫になる。朝起き上がるだけで精一杯で、食事や着替えのような些細なことさえ、時には大きなハードルに感じられます。そんな日々が続くと、時間が止まったような感覚に襲われ、「自分はこのままずっと抜け出せないんじゃないか」と絶望する瞬間もあります。
そんな中で、ふとしたきっかけで訪れる躁の時期は、まるで別世界のようです。頭の中の霧が一気に晴れて、考えが次々と浮かび、アイデアが止まらなくなる。普段なら先延ばしにしてしまう仕事も自然と手が進み、「あれもこれもやってみたい」と前向きな気持ちが湧き上がってくる。体も軽く、朝から散歩に出かけたり、予定を詰め込んでも疲れ知らずで過ごせたりします。うつの時とは全く別人のような自分がそこにいて、「これが本当の自分なんじゃないか」と錯覚するほどです。
この「軽やかな自分」を一度でも経験してしまうと、うつの時期にどうしても恋しくなってしまうんです。「あのときの集中力があれば」「またあの前向きな自分に戻れたら」と、何度も頭の中で繰り返し思い出してしまう。まるで好きな音楽がふと頭の中で流れてくるように、あの高揚感が心の奥底からよみがえってくるのです。
でも、冷静に考えると、それが「病気の症状」であることもわかっています。高揚感の渦中にいるときは自分ではなかなか気づけませんが、後から振り返ると無理を重ねていたり、周囲との関係が乱れていたり、生活リズムが崩壊していたりすることが多い。どれだけ前向きに感じても、それは「本来の自分」ではなく、「病気が作り出した一時的な状態」だという現実があります。
それでも心のどこかで、躁の自分を「理想」として追い求めてしまう自分がいます。たとえそれが症状だと理解していても、「あの時の自分こそ本当の自分なのでは?」という思いが完全には消えないのです。この矛盾した気持ちは、多くの双極性障害の当事者が抱えているものではないでしょうか。
「躁の自分」と「うつの自分」、どちらが本当の自分なのか——。私もまだその答えを見つけられていません。ただ、最近は少し考え方が変わってきました。たとえば、躁の状態で出てくる前向きさやアイデアは、確かに症状の一部かもしれませんが、その中にも「自分の本質的な力」や「本来持っている可能性」が隠れていると感じることがあります。逆に、うつの時期の自分も、ただの「マイナスな状態」ではなく、心や体のサインを大切に受け取って休むための時間なのかもしれません。
つまり、どちらの状態も「本当の自分」の一部であり、病気を通して自分の幅を知っていくプロセスなのではないかと、今は少しずつ思えるようになってきました。もちろん、その境界線を見極めるのは簡単ではありません。でも、症状と自分を切り離すのではなく、どちらの状態の自分にも意味があると受け入れられたとき、少しだけ心が軽くなる気がします。
私もこの気持ちと折り合いをつける方法をまだ探している途中です。でも、こうして言葉にしてみるだけで、どこか整理されていく感覚がありますし、「自分だけじゃない」と思える瞬間があるだけで、前に進む力が湧いてきます。
同じように「躁が恋しい」と感じている人の言葉を読むと、心が少し軽くなるものです。私が共感した記事をひとつご紹介します。興味のある方は、ぜひ読んでみてください。
👉 《双極性障害》躁が恋しい
躁のときの自分が忘れられず、その感覚をもう一度味わいたいと願ってしまう――そんな複雑な心情を丁寧に綴った体験談です。共感できる部分がきっと見つかると思います。
記事を読む