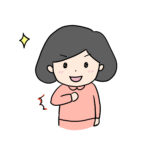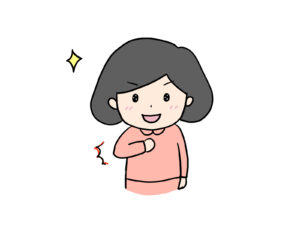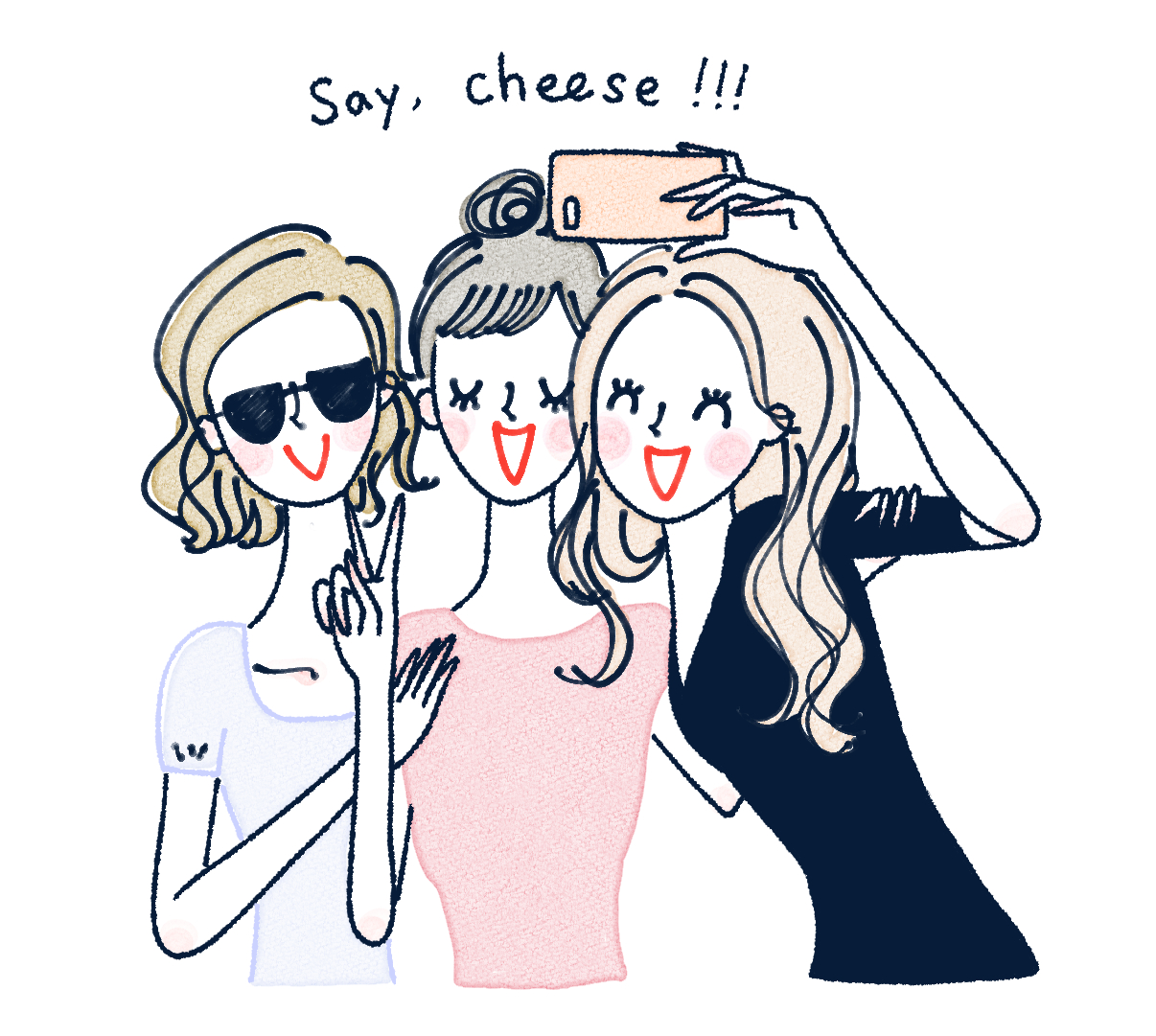
不登校ルーティーンという言葉を知っていますか?
言葉の通り、不登校の子どもたちの生活習慣を示す言葉です。
実はこの「不登校ルーティーン」をめぐって、一部の子どもたちの間でトラブルが起きているのです。
私は子どもたちの置かれている世界を知るために、定期的にTikTokなどの若者が使うSNSをチェックしています。そこで「不登校ルーティーン」と検索すると、不登校の子の投稿がかなり出てくるのです。
投稿内容や投稿者の立場はさまざまで、
朝起きて散歩をして勉強をするというような理想的な習慣をアップしている人もいれば、
昼夜逆転生活やゲーム三昧の生活を載せている人もいます。
不登校当事者が投稿しているものもあれば、そうでない人が不登校を批判するために投稿しているケースも見られます。
ここからが、子どもたちの間で問題になっている点、そして私自身も心配していることなのですが、
不登校ルーティーンに関する投稿に誹謗中傷のコメントが書かれているのをよく見かけます。
主な衝突は、学校へ通っている子と不登校の子との間で起きています。
容易に想像がつくかと思いますが、言ってしまえば
「学校に行っていないなら楽しいことをするな」
という考え方です。
子どもが言いそうなことだなぁ、ははは。
大人からすれば小さなたわごとに見えるかもしれません。
けれどもこの問題には、現代の子どもたちの心の叫びが凝縮されているように思えてなりません。
不登校への理解はこの10年ほどでずいぶん進み、
私たち大人からすると「不登校=大きな問題」という感覚は薄れつつあります。
しかし、今まさに学校生活の中で生きている子どもたちが見ている世界はきっと違うのです。
TikTok上での子どもたちのやりとりを見ていると、よくこんな言葉を目にします。
「学校に行っている私は偉い。不登校は偉くない。」
――「偉い」。
子どもたちにとって学校が心から楽しく、安心できる場所であれば、きっと「偉い」なんて言葉は出てこないはずです。
もし学校がディズニーランドのようにワクワクする場所だったら、「行っていて偉い」なんて表現のしようがありません。
「嫌なこと(=学校に行く)を頑張っている自分は偉い。」
――きっと、そんな論理なのでしょう。
この問題から見えてくるのは、不登校ルーティーンに中傷的な発言をしている子たちも、実は「隠れ不登校」なのではないかということです。
いつから学校は、子どもたちにとって苦痛な場所になってしまったのでしょう。
第二次世界大戦中を生きた私の祖母は、子どものころ「学校に行きたくて仕方がなかった」とよく話していました。
教育を当たり前に受けられるようになった日本で、現代の子どもたちは学べることの尊さを実感できているのでしょうか。
不登校ルーティーンに向けられたコメントの数々は、学校教育という、自分たちには変えることのできないシステムへの不満の表れのようにも見えます。
私たち大人がこの問題に真摯に向き合い、
これからの学校がどのようにあるべきなのか、考えていかなければなりません。