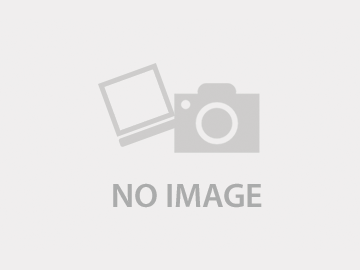「最初はうつ病だと言われていたのに、後から双極性障害と診断が変わった」──このようなケースは決して珍しくありません。むしろ、双極性障害の患者の多くが、最初は「うつ病」として治療を受けているといわれています。本記事では、その理由や背景、診断が変わるまでの経緯について、客観的な視点から解説します。
うつ病と双極性障害の違い
うつ病は「気分が落ち込む」「意欲が出ない」といった抑うつ状態が続く病気です。一方、双極性障害は「うつ状態」と「躁状態(または軽躁状態)」を繰り返すことを特徴とします。両者の「うつ期」は非常によく似ており、初診時には区別がつきにくいのが現実です。
特に双極性障害Ⅱ型の場合は、躁状態が比較的軽く「ちょっと調子がいい」「よくしゃべる」程度にしか見えないことも多く、本人も自覚していないケースがあります。そのため、「うつ状態」だけが目立っている段階では、医師も「うつ病」と診断せざるを得ないことがあります。
なぜ診断が変わるのか
診断が「うつ病」から「双極性障害」に変わる大きな理由は、時間の経過とともに躁(または軽躁)エピソードが確認されるからです。初診時に抑うつ症状しか見えていなかったとしても、数年の経過観察のなかで「気分が異常に高まる」「衝動的な行動が増える」といった兆候が見られると、診断が見直されることになります。
また、家族から「以前、妙に活動的だった時期があった」と聞き取れたり、本人が思い出すことで躁状態の存在が明らかになる場合もあります。診断の変更は、決して「誤診」ではなく、病気の全体像が見えた結果といえるでしょう。
診断の違いが治療に与える影響
診断が変わることは、治療方針にも大きく影響します。うつ病では一般的に抗うつ薬が中心となりますが、双極性障害では気分安定薬が治療の主軸になります。誤って抗うつ薬だけを使い続けると、躁転(躁状態への移行)を引き起こすリスクもあるため、診断の見直しは非常に重要です。
うつ病から診断が変わったときに大切なこと
「双極性障害」と診断されたとき、多くの人がショックを受けます。しかし、診断名が変わったということは、より正確な治療に近づいたということです。重要なのは、医師とよく相談し、治療方針を一緒に考えていくこと。そして過去の自分を責めず、「今ここからどう向き合うか」に意識を向けることです。
また、診断を受けた本人だけでなく、家族や周囲の人も正しい知識を持つことが支えになります。双極性障害は適切な治療と生活の工夫によって、安定した生活を送ることが可能な病気です。
関連する体験談・記事紹介
👉 鬱病、鬱病から双極性障害になった話
うつ病だと思っていたら実は双極性障害だった――診断が変わるまでの実体験が綴られています。
記事を読む
👉 双極性障害~うつ病から入院をして分かった病名の体験談
入院を経て初めて病名が分かった体験談。診断が変わる経緯がリアルに描かれています。
記事を読む
※この記事は医療行為を推奨するものではありません。正確な診断・治療については必ず医療機関・専門医にご相談ください。
参考文献・参考サイト
- 厚生労働省「こころの病気について」https://www.mhlw.go.jp/kokoro/speciality/detail_bipolar.html
- 日本うつ病学会 双極性障害診療ガイドライン 2020
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5).