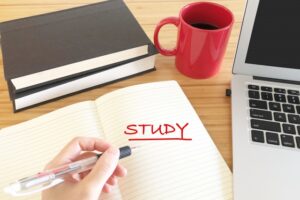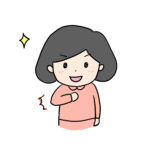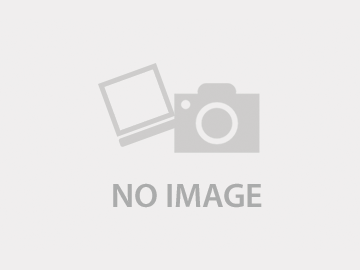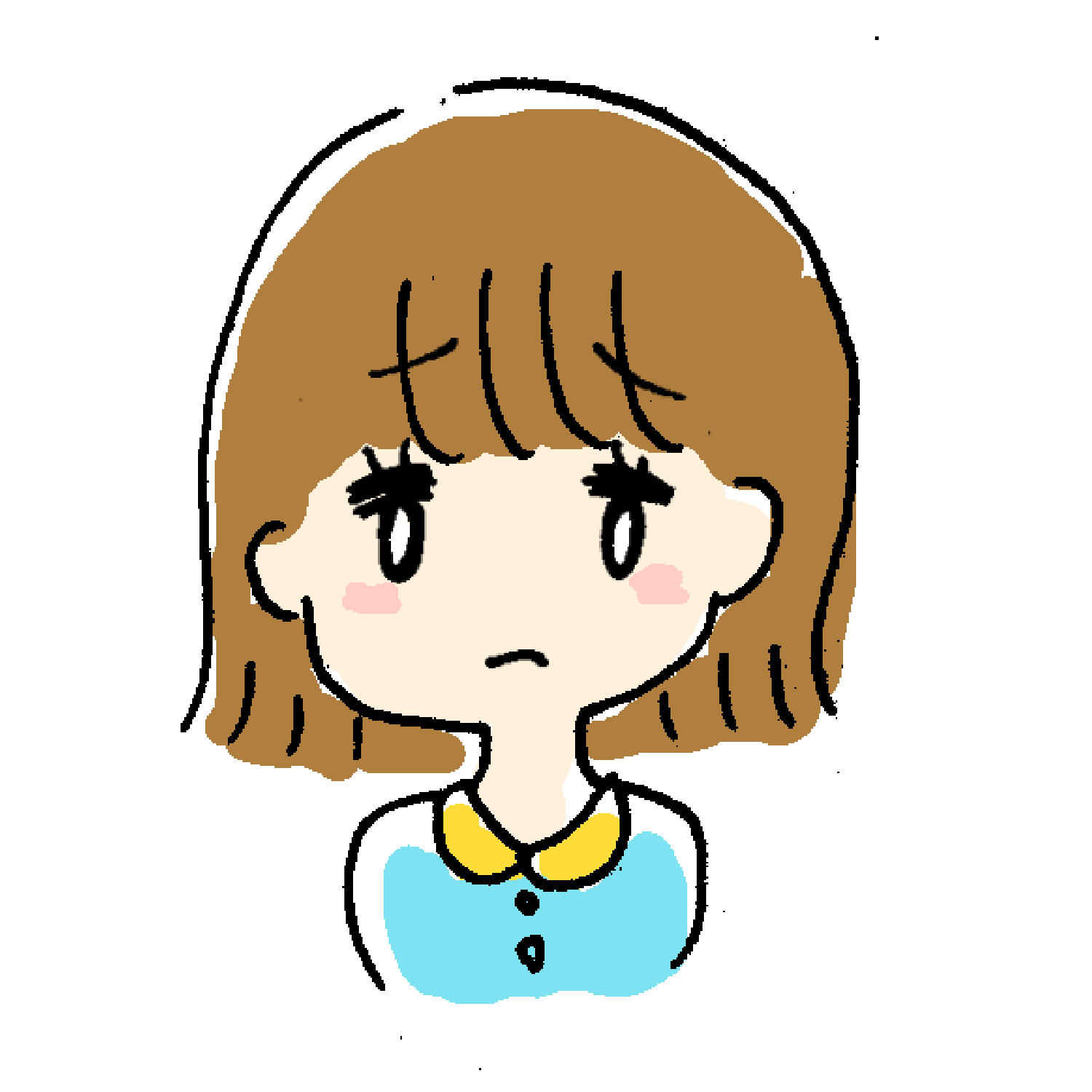
もくじ
はじめに — 「働き方」と「価値」は別ものです
働き方には正社員、パートタイム、アルバイト、フリーランスなどいくつもの形があります。しかし「その人の価値」を雇用形態だけで測る風潮は根強く、特にパート・アルバイトで働く人が低く見られがちです。本稿では、その誤解を解き、背景や実態を整理するとともに、社会としてどう向き合うべきかを考えます。
なぜ「下に見る」イメージが生まれるのか
歴史的には終身雇用や年功序列を前提にした正社員中心の労働モデルが広まりました。その結果、安定性や昇進の機会が正社員に偏り、社会的ステータスと結び付けられてしまいました。加えて、賃金や福利厚生の差、勤務時間の違いが「仕事の重要度=評価」という誤解を助長しています。
個人の事情と働き方の選択肢
精神疾患、慢性疾患、育児や介護、学業、家庭の事情など、正社員としてフルタイムで働けない背景は多様です。そうした事情を抱えながらも労働市場に参加している人々は、社会に必要な役割を果たしています。働ける範囲で貢献したいという意思そのものが尊重されるべきです。
パート・アルバイトの「価値」を正しく見るための視点
時間当たりの労働、生産性、職務内容、経験やスキルの有無など、評価軸は多面的です。例えば接客、介護、教育、清掃、物流など、社会インフラを支える現場の多くはパートやアルバイトで成り立っています。職務の社会的必要性や成果を基準にすれば、「雇用形態=価値」という単純な図式は崩れます。
心理的なダメージと社会的排除のリスク
「下に見られる」ことで自己肯定感が下がり、症状の悪化や離職につながる場合があります。また、職場での発言機会が制限されたり、教育・昇進の機会に恵まれなかったりすると、長期的なキャリア形成が阻まれます。こうした連鎖を社会で断ち切ることが重要です。
企業と社会ができること
企業は雇用形態に関わらず公平な評価基準を設け、研修やキャリアパスを開くべきです。自治体や国は柔軟な就労支援制度や医療・介護との連携を強化し、働きやすい環境を整備する必要があります。私たち市民も「ありがとう」「助かったよ」といった日常の言葉で価値を伝えられます。
当事者の声を可視化することの力
個々の体験談やブログ、SNSでの発信は偏見を解く強力な手段です。実際の成功事例や工夫、困りごとを共有することで、同じ境遇の人が選択肢を見つけやすくなり、周囲の理解も進みます。
個人ができるアクション
職場での言葉遣いや態度を見直す、評価基準の透明化を提案する、当事者的な話を聞く場を作る──こうした小さな行動が文化を変えます。また、自分自身がパート・アルバイトであれば、自分のスキルや成果を可視化するポートフォリオを作るのも有効です。
結論 — 「尊重」と「機会の平等」を社会の基盤に
正社員かパートかというラベルだけで人を測るのは、個人の事情や社会的貢献を見逃すことにつながります。多様な働き方を当たり前に受け入れ、誰もが尊厳を保ちながら働ける社会こそが本当に豊かな社会です。評価は役割と成果、機会の平等を基準にするべきです。
紹介:時短勤務3年目。肩身がせまい、から抜け出した方法
時短勤務という制約の中で感じる孤立感・葛藤を正直に綴る筆者が、「肩身の狭さ」から少しずつ抜け出すために実践した考え方や行動を共有してくれます。共感できる部分も多く、励みになる内容です。
https://note.com/suzu252/n/n5dbedfd69916